【京都の伝統技術】手描き友禅・京友禅型染・京紅型・京鹿の子絞り・西陣織・京繍・つまみ細工をご紹介

京繍(きょうぬい)


京繍は、十五種類の針と多色の糸を使って布地など模様を縫い表す装飾技法。平安遷都とともに刺繍をするための職人を抱えた縫部司(ぬいべのつかさ)が置かれ、宮廷貴族から武士、財力を持った庶民までを対象に衣服の装飾に用いられたのが始まりです。高度な技術によって製作される京繍が、京都の着物をより一層華やかなものにしてくれます。
京繍の工程(染色工程)
構想・図案→染色加工→蒸し・水元→印金・刺繍加工→補正→完成
京繍の工程(京繍工程)
糸染→糸巻→糸撚(いとより)→繍加工(ぬいかこう)→完成
西陣織


西陣織は京都がはぐくんできた高級絹織物であり、先染(注1)の紋織物(注2)の総称です。現在、十二品目の織り技法が伝統工芸品の指定を受けています。西陣という名は、室町時代の応仁の乱の時、西軍が本陣とした場所に、乱の後、職人が集まって織物をしたことから付けられました。
注1:糸を先に染めること
注2:経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を複雑に組み合わせて、模様を織り出した織物のこと
西陣織の工程
図案→紋意匠図→紋掘→紋意匠図(パソコン)→CG/FD(フロッピーディスク)→撚糸(ねんし)→糸染→糸操(いとくくり)→整経(せいけい)・緯巻(ぬきまき)→綜絖(そうこう)→綴機(つづればた)・手機(てばた)・力織機(りきしょくき)→整理加工→完成
つまみ細工

つまみ細工とは、江戸時代に始まった布工芸の一つで、小さなハギレをつまんで花にしていく細工です。小さな花びらが並んで花になる様子は圧巻で、舞妓の花かんざしや、七五三・成人式、結婚式の髪飾りなどに用いられます。
つまみ細工の工程
裁断→つまみ→葺き(ふき)→仕上げ→完成
時代の変化とともに生まれてきた様々な技術。その技術は現代の職人の方にも受け継がれております。きものサローネでは実際にワークショップもあり、連日多くの方が体験をされておりました。
着物が出来上がるまでにある、様々な工程を知ることもまた着物の楽しさの一つですので、今後も趣通信で様々な技法などご紹介していければと思っております。
協力:京都染織青年団体協議会ホームページ:http://www.wasou.or.jp/kyogikai/
編集部おすすめ記事ピックアップ
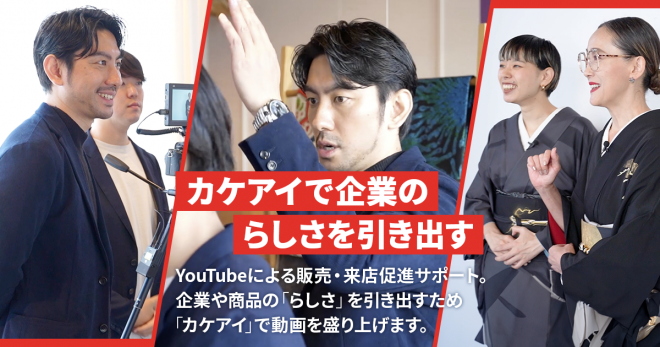
<YouTube動画で販売促進|着物業界>
YouTube運用代行「カケアイ」
<YouTubeを活用して着物の販売促進をお考えなら!>
おすすめYouTube運用代行会社10選










趣通信編集部のアカウントです。いま、楽しむ日本の趣-omomuki をコンセプトに着物を中心に日本の伝統文化や和にまつわる話題を発信していきます。
その他の記事を読む